鈴木俊明先生の体幹講演で得たもの
8月12日・13日の鈴木俊明先生の講演では、多くのことを得ることができました。
そのことについて、私なりに得たことをまとめてこのブログで紹介させて頂きます。
下記の内容は、読んでくれた方に必ず役立つと思いますが、その解釈には私の個人的な考えが多分に含まれています。
鈴木先生にご迷惑がかからないためにも、あらかじめそのことを踏まえて、読んでみてください。(^_^)
● 中枢神経疾患の治療における筋を賦活する手技の重要性
まず体幹をコントロールするにあたり、体幹筋を賦活する手技が多いということを感じました。
鈴木先生自身は、筋を緩めることも、賦活することも、両方自在にできるのですが、賦活する手技を使うことの方が多いようです。
これまでたくさんのトップランナーを見てきましたが、臨床では、筋を賦活したり強化したりする手技も、筋を緩めたりストレッチしたりする手技も、両方必要です。
しかし特に運動器の分野では、どちらかというと筋を緩めたりストレッチしたりする手技の方が重要だと私は考えていますし、これまで聞いてきた講演でもそういった技術を紹介する先生が多かったように思います。
これは運動器疾患においては、多くは麻痺があるわけではないので、使っていない筋があったとしても、アライメントや、筋・関節のバランス調整をして、その筋が使える環境を作ることの方が重要であり、使える環境を作ることができれば、筋が自動的に賦活されると言えるのかもしれません。
だから、筋を賦活したり強化したりする手技も、筋を緩めたりストレッチしたりする手技も、両方必要なのですが・・・
運動器の分野では、どちらかと言うと、筋を緩める技術の方が重要であると私は考えています。
実際に、攣縮している筋を緩めることができたり、短縮した筋腱をストレッチングする技術を持っていると、それだけで効果的に痛みを取ることができますし、それだけではなく筋肉のバランスが変わり、使っていない筋肉が使えるようになることはよくあることです。
一方、中枢神経疾患の場合は、事情が異なってきます。
なぜなら、麻痺などによって、筋が使えない状態になるからです。
だから、まずは筋を賦活し、収縮の感覚を取り戻すことが重要だと言えるのかもしれません。
ではどうしたら、使えなくなっている筋を賦活することができるのか?
鈴木先生の講演では、このことについて多く触れていただきました。
紹介していただいた知見と技術は、全て鈴木先生が自身の研究によって、実証しているものばかりで、研究と臨床が本当に結びついていることがすごいなと感じました。
また中枢神経疾患の場合、筋の収縮感覚を促通した上で、使える環境を作っていくということが重要だと改めて痛感しました。
● 自身の研究によって、確信を持った理論を持つことの重要性
鈴木先生の講演では、常識からは逸脱していると思えることが多いと思います。
たとえば、一般には座位をとるとき、多くの臨床家が体幹の安定性を作るために腹部の筋肉が重要であると考えています。
しかし、鈴木先生は「座位を取るだけなら、腹筋はほとんど不要である。背筋だけが必要である。」と述べています。
誤解して欲しくないのは、これは腹部の筋が不要と言っているのではありません。
あくまでも安定した座位を取るだけであれば、腹部の筋は不要であり、最長筋・多裂筋などの背面の筋がうまく働いていれば、安定した座位が取れるということです。
確かに力学的に考えれば、うなずける話です。
座位で姿勢筋緊張が低いケースを多く見受けますが、まず我々が取り組むことは、最長筋や多裂筋を復活し、安定した座位としての姿勢セットを作ることが重要であることが分かります。
しかし、こうした常識とは違った理論も、自分自身の研究で確認しているからこそ確信を持って患者に行うことができる。
そういったことの重要性を学んだ気がします。
● 筋の作用を部位ごと詳細に把握することで臨床の幅が広がることの重要性
通常の座位では多裂筋が主に働き、姿勢保持をしています。
しかし腰椎が屈曲した肢位の座位では、腸肋筋の活動が大きくなり、それだけではなく、多裂筋の活動が小さくなります。
つまり・・・
この2つの筋は、トレードオフする関係にある。
このことは、私の臨床でもめちゃくちゃヒントになりました。
というのは、以前から、腰部の筋の張りを訴える患者の場合、多裂筋付近に張り感を訴える患者と、やや外側の腸肋筋に張り感を訴える患者がいることは感じていました。
今回の鈴木先生の話を聞いたことで、私の中でアイディアが色々と浮かび、治療する上でのヒントが得られたように思います。
また、「きれいな座位とは最長筋と多裂筋が働いて、腸肋筋が働かない肢位のことである」と述べていたことも、臨床的なアイディアを頂いたように思います。

● 結論的視点
中枢神経疾患のリハビリで、3単位を使うことはよくあります・・・。
でも本当に我々は、この3単位という時間をしっかり考えて・・・、そして、その日その日ごとに明確な結果を出して、治療を行っているでしょうか。
途中でもうやることがなくなって・・・、ただ一緒に歩くだけ、ただ一緒におしゃべりするだけで時間を費やしてはいないでしょうか。
我々療法士は学ぶことがたくさんあります。
そして学べば学ぶほど、考えることがたくさんあることが分かります。
そして何より、考えて治療すればするほど、患者の笑顔が増えていくことが分かります。
そこにたどり着くためには、苦しいこともあると思います。
でもそれがプロフェッショナルとしての仕事なんだと私は考えます。
なぜなら・・・、プロフェッショナルはそんなに甘いものではないからです。
まだまだ書き足りないくらいで、伝えたいことがいっぱいあるのですが、今回は、このぐらいにさせていただきます。
私も明日から臨床で感じたことをいろいろな形で実証していくことで、確信の持てる理論を増やしていきたいと思います。
そして、「謙虚」、「ひたむき」を忘れずに、臨床と向き合っていきたいと思います。
追伸
下記は、アメフト元日本代表の東松瑛介選手です。本人に許可を頂いたので、掲載致します。どのスポーツでも貢献できるようにまだまだ成長していきます(^_^)

私の推薦する書籍
以下は私がおすすめする書籍です。
園部俊晴の臨床『徒手療法ガイドブック』 Ⅱ 膝関節・下腿・足関節・足部編
【初回限定特装版】限定カバー・ポッドキャスト付き
1万部を超えたベストセラー『園部俊晴の臨床』シリーズの最新作!
臨床で「目の前の患者がその場で変化する治療技術」を多くのセラピストが求めている!
好評を博した前作に続く、待望の続編!膝関節、下腿、足関節、足部の臨床でよく見受ける病態にフォーカスし、結果を出せる技術を解説します。
徒手療法の本質である「滑走性と伸張性の改善」を習得することで、治療のセンスや手先の器用さに関係なく、誰でも成果を出せる技術を習得できる。
その極意が本書には記されています。
本書は、第3水準の評価までのプロセス(痛みの原因組織の同定と除去)を実践するための、実践的で再現性の高いテクニックを厳選して紹介しています。
目の前の患者の「痛み」を確実に変えることができれば、これまで以上に「可動性・柔軟性の低下」や「運動機能の低下」などの症状を変えられる体験が必ずできるはずです。
目次
第Ⅰ部 基本が分かれば誰でもできる!滑走性と伸張性のテクニックを手に入れる重要性
- 第1章 滑走性と伸張性のテクニックを手に入れる重要性
- 第2章 最高のセラピストになるための絶対条件「第3水準の評価とは」
第Ⅱ部 滑走性・伸張性 改善テクニックの実際
- 第1章 膝関節への滑走性・伸張性改善テクニック
- 第2章 下腿への滑走性・伸張性改善テクニック
- 第3章 足関節・足部への滑走性・伸張性改善テクニック
結果の出せる評価と治療 ー末梢神経とエコーから紐解く痛みの解釈ー
「痛みの原因」を明確に!
医師と理学療法士が「エコー」を共通言語に挑む、次世代の運動器診療
■あなたは、患者の痛みの“本当の原因”を明確にした上で、治療を行えているだろうか?
■「腱板の機能が低下している」「体幹が弱い」「骨頭が前方に偏位している」といった説明で運動療法を行っているだけでは、痛みの本当の原因には、たどり着いていないかもしれません。
■痛みの原因を明確にするとは、それが「構造が壊れた痛みなのか?」「神経による痛みなのか?」「脳が生み出している痛みなのか?」を深く見極めることです。この視点を持たずに行う運動療法は、改善への遠回りになってしまう。
■その鍵は、「エコー」という共通言語を武器に、“痛みを1つの線で捉える”こと。これまでレントゲンやMRIでは見えなかった病態が、動的な観察を可能とするエコーによって「見える化」され、診断と治療の質を大きく変えつつあります。
■本書は、整形外科とリハビリテーションの新たな融合の形を示す、まさに次代の医療のあり方を指し示す一冊です。この一冊が、これからの医療を大きく変えるきっかけとなることを願って。
—TOPIX—
本書は、痛みの原因を「侵害受容性疼痛」「神経障害性疼痛」「痛覚変調性疼痛」の3つに大別し、それぞれの病態解釈と具体的な評価・治療法を、豊富な図表と実例とともに解説します。特に、画像所見だけでは捉えきれない「末梢神経の痛み」に焦点を当て、その「滑走性」を引き出す理学療法の実践方法を、肩関節、膝関節、腰殿部痛の症例を通して詳細に紹介します。
第1章 疼痛治療に対するパラダイムシフト 〜医師から理学療法士へ伝えたいこと〜
- エコーを共通言語にした医師と理学療法士の融合診療
- 運動器診療の現状
- 運動器診療の患者満足度
- 運動器診療の現状と共通言語の重要性
- 痛みの原因を明確にするための手順
- 痛みを3つに大別する
- 痛みを1つの線として捉える
- 侵害受容性疼痛
- 神経障害性疼痛
- 痛覚変調性疼痛
- 痛みの解釈
第2章 末梢神経を軸とした肩関節に対する理学療法
- はじめに
- 末梢神経を軸とした病態の考え方
- 臨床推論の迷路
- 理学療法の戦い方を考える
- 病態解釈に必要な基礎知識
- 末梢神経と身体所見の考え方
- 超音波画像の描出の意味
- 腱板を描出する意味
- 末梢神経を軸にした理学療法
- 末梢神経を軸にした理学療法の考え方
- SM後の理学療法
- 腋窩神経の痛みに対する理学療法
- 肩甲上神経の痛みに対する理学療法
- おわりに
第3章 末梢神経を軸とした膝関節に対する理学療法
- はじめに
- 共通言語の重要性とアライメント
- 共通言語の重要性
- アライメントを重視する
- 痛みに対する共通言語をもつ
- 痛みの原因を明確にするための基礎知識
- 単純X線像による変形と痛みは必ずしも一致しない
- 痛みを考察するための基礎知識
- 侵害受容性疼痛を考察するポイント
- 神経障害性疼痛を考察するポイント
- まとめ
- 膝前面部痛の病態解釈に必要な機能解剖
- 膝蓋下脂肪体の痛みを再考する
- 膝前面部痛を理解するための解剖学的知識
- 膝関節前面の末梢神経
- 末梢神経を軸とした理学療法
- 末梢神経に対する評価方法
- 伏在神経膝蓋下枝に対する理学療法
- 内側広筋枝に対する理学療法
- 内側膝神経に対する理学療法
- おわりに
第4章 末梢神経を軸にした腰殿部痛に対する理学療法
- はじめに
- 腰殿部痛の原因を明確にするためのヒント
- 病態を2つに大別する
- 画像で分かる腰殿部痛
- 画像では分からない腰殿部痛
- 病態解釈に重要な機能解剖学
- 腰椎椎間板ヘルニアと坐骨神経痛の病態解釈
- 仙骨神経後枝外側枝による仙腸関節障害
- 末梢神経を軸にした理学療法
- 腰殿部痛と下腿外側部痛を訴える患者の理学療法
- 仙腸関節付近の痛みを訴える患者の理学療法
- 腰殿部痛を1つの線で捉えた理学療法
- おわりに
—著者—
- 宮武和馬
- 河端将司
- 宮田徹
- 齊藤正佳
ご購入はこちら
ねこ背病 放置する人から老いていく
【2025年8月発売】「もう年だから…」と諦めていませんか? 1日1分から始める!理学療法士・園部俊晴の【ねこ背改善メソッド】で、見た目も体も若返り、健康でイキイキとした毎日を取り戻す!
ふと鏡に映るご自身の姿勢に「背中が丸くなっているかも…」と気づいたことはありませんか? ねこ背は単なる見た目の問題ではありません。肩こりや腰痛の慢性化、股関節やひざの曲がり、転倒リスクの増加、活動範囲の縮小など、日常生活の質に直結する様々な悪影響をもたらします。歳を重ねるほど体のバランスを取る力が低下し、ねこ背が原因で身体機能全体が弱まる悪循環に陥ることもあります。また、ねこ背の人は体幹が「硬い」という特徴も持っています。
しかし、ねこ背は「歳だから仕方がない」と諦めるものではありません! 本書は、リハビリ現場で多くの高齢者を診てきた理学療法士、園部俊晴が、誰でも無理なく実践できる画期的なアプローチを紹介します。長年の経験から「ただ背中を伸ばせば治るわけではない」と提唱し、体幹・肩・股関節・ひざと全身の連動性を意識し、バランスよく整えることを重視。体全体の機能改善こそが、真のねこ背改善に繋がると説きます。
【本書で得られる効果と期待】
- 見た目の若返り:姿勢が改善され、若々しい印象を取り戻せます。
- 痛みからの解放:肩こり、腰痛、ひざの痛みの原因となる体の負担を軽減します。
- 転倒リスクの軽減:体幹でバランスがとれるようになり、転倒しにくい体に。
- 活動範囲の拡大:体が軽く動きやすくなることで、イキイキとした生活を送れるようになります。
【本書の5つの主要アプローチ】
たった1日1分、各エクササイズは30秒程度でOK! 該当ページ内のQRコードをスマートフォンで読み取ると、解説付きの映像で確認できるため、正しいフォームで無理なく続けられます。
- 体幹を伸ばす・筋力を改善するアプローチ:ねこ背改善の基本となる体幹の柔軟性・筋力を取り戻します。
- 肩周りを柔軟にするアプローチ:ねこ背と関係の深い「巻き肩」を改善し、腕の上げにくさを解消します。
- 股関節とひざを伸ばすアプローチ:体幹と相互に影響し合う股関節とひざの柔軟性を高めます。
- 下肢の筋力を改善するアプローチ:特に重要な「大殿筋」や「大腿四頭筋」など、足腰の筋肉を強化し、体の曲がりを食い止めます。
さらに、本書では「正しく立ち、正しく座る」といった基本の姿勢や、体幹をスムーズに前へ運ぶ「正しい歩き方」に加え、デスクワークやスマホ使用時など、日常生活でねこ背になりやすい場面ごとの改善ポイントも丁寧に解説しています。
「すべてを完璧に行うこと」ではなく、「自分に合ったエクササイズを1つでも見つけて続けること」が大切です。あなたの体は、きっと変わるはずです。
『もう年だから』と思う前に、ぜひ本書のメソッドを取り入れてみてください。健康でイキイキとした毎日の第一歩を、今日から一緒に踏み出しましょう!
著者紹介
園部 俊晴(そのべ としはる)
理学療法士
コンディション・ラボ 所長
運動と医学の出版社 代表取締役社長関東労災病院リハビリテーション科で26年間勤務ののち、『コンディション・ラボ』を開業。足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。一般の人だけでなく、スポーツ選手にまで幅広く支持され、自身の治療院は約1年待ち。多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛ける。身体の運動連鎖や歩行に関する研究および文献多数。著書多数。専門家からの評価も高く、全国各地で講演活動を行う。
- 【主な著書】
- 「園部式脚の痛み・しびれ改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「ひざ痛探偵 謎はすべて解けた!(運動と医学の出版社)」
- 「園部式歩行改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「園部式 脊柱管狭窄症 改善メソッド(彩図社)」
- 「園部式 ひざ痛 改善メソッド(彩図社)」
- 「つらいひざ痛が1分でよくなる! ひざ下リリース (わかさ出版)」
- 「お尻の痛み・しびれ 1分でよくなる 最新最強 自力克服大全(わかさ出版)」
- 「リハビリの先生が教える!健康寿命を10年延ばすからだのつくり方(運動と医学の出版社)」など著書多数
目次
- はじめに
- 第1章 ねこ背の影響は姿勢だけではない
- ねこ背になると、何が問題なのか
- ねこ背を改善するには、体全体の機能を改善する必要がある
- ねこ背を改善する5つのアプローチ
- 第2章 ねこ背改善のためのアプローチ
- 体幹を伸ばすアプローチ
- 体幹の筋力を改善するアプローチ
- 肩周りを柔軟にするアプローチ
- 股関節とひざを伸ばすアプローチ
- 下肢の筋力を改善するアプローチ
- 第3章 日常生活でねこ背を改善するアプローチ
- 日常生活のあらゆる場面でねこ背は改善できる
- 正しい座り方
- 正しい立ち方
- 正しい歩き方
- 要注意! ねこ背に気をつけたい日常場面
- エクササイズ一覧
- おわりに
ご購入はこちら
理学療法超音波学 vol.3
待望のシリーズ第3弾!
臨床に”視える力”を。
超音波という”目”が治療を変えていく。■ 理学療法における超音波技術の進化を象徴し、第5回日本運動器理学療法超音波フォーラムで注目を集めた最新トピックスを、豊富な図表と動画で徹底解説!
■ 「足」、「膝」、「上肢」の3つの分野に関する計13タイトルを厳選して収載。「超音波技術は、従来では把握しきれなかった詳細な筋骨格系の構造と機能の動的な情報を提供」し、「より的確で効果的な治療計画を立案することが可能」になります。
■ 超音波画像による評価バリエーションを増やすことで、痛みを発している原因へのアプローチの“解像度”が大幅に向上! 理学療法士の皆さまが「臨床現場でのさらなる飛躍」を遂げるための、不可欠なツールとなることを願っています。
Chapter 1: 足
- 超音波画像による足関節背屈制限の病態評価と理学療法の実際
- ハイドロリリースの生体力学
- 長母趾屈筋腱の周囲脂肪組織におけるエコー動態評価のための解剖学的検討
- 足関節捻挫後に生じる前外側部痛と中間足背皮神経症状との関連性について
- 足関節後方部痛に対する超音波動態観察と治療戦略
- 扁平足における荷重に伴う足部周囲筋の形態的・力学的特性
Chapter 2: 膝
- ACL再建術後膝に対するleaf spring exerciseの安全性 ― 超音波画像診断装置を用いた大腿骨-脛骨位置の評価 ―
- 持続的および間欠的等尺性膝伸展運動が大腿四頭筋の安静時筋弾性と筋内血流に与える影響
- 股関節周囲筋の筋硬度から考えるTHA術後早期の理学療法
Chapter 3: 上肢
- 脊髄神経後枝内側枝由来の頚部痛を考える ― 頚椎伸筋群の機能評価に着目して ―
- 大学野球選手における上腕骨頭後外側不整像の病態解釈
- 投球障害肘に対する局所的アプローチ
- 母指CM関節症の病態とリハビリ
—監修—
- 日本運動器理学療法超音波フォーラム
—編集代表—
- 福井 勉(文京学院大学)
—編集—
- 浅野 昭裕(うめだ整形外科)
- 小柳 磨毅(大阪電気通信大学)
- 谷口 圭吾(札幌医科大学)
- 林 典雄(運動器機能解剖学研究所)
- 村木 孝行(医療法人はぁとふる 運動器ケア しまだ病院)
—執筆者一覧—
- 澳 昂佑(川崎医療福祉大学)
- 塩泡 孝介(KKR札幌医療センター/札幌医科大学整形外科)
- 大坪 英則(札幌スポーツクリニック)
- 中尾 学人(札幌医科大学大学院 保健医療学研究科)
- 河田 龍人(中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法学科/立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科)
- 篠原 靖司(立命館大学 スポーツ健康科学部)
- 二村 英憲(名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科)
- 久我 友也(メディカルベース新小岩)
- 小林 匠(群馬大学大学院 保健学研究科)
- 築田 英紀(行岡病院)
- 小柳 磨毅(大阪電気通信大学)
- 山形 一真(整形外科北新病院)
- 谷口 圭吾(札幌医科大学 保健医療学部 理学療法学科)
- 長南 晴樹(慶友整形外科病院 リハビリテーション科)
- 水野 弘道(たなけん脊椎・眼科クリニック リハビリテーション科)
- 内田 智也(トヨタ記念病院 トヨタアスリートサポートセンター/大阪大学医学系研究科健康スポーツ科学講座 運動制御学教室博士後期課程)
- 三輪 智輝(メディカルベース新小岩)
- 岩本 航(江戸川病院スポーツ医学科)
- 大森 康高(西川整形外科)
ご購入はこちら
もう人任せにしない!腰痛の原因を見つけて治す!セルフマネジメント術!~腰痛との向き合い方は、自分に合ったものを選ぶ時代へ~
その腰痛、『性格』があるって知っていましたか?」
長年、腰痛の原因が分からずに湿布や痛み止めで「なんとなく」やり過ごしていませんか?
本書は、延べ20年以上にわたり全国から腰痛患者が集まる人気理学療法士・成田崇矢先生が、実際の臨床経験をもとにたどり着いた“腰痛の正体”と“セルフマネジメントの極意”を、わかりやすく解説した一冊です。書籍のポイント
- 腰痛には“4つのタイプ”がある! 椎間関節・仙腸関節・椎間板・筋・筋膜――自分の腰痛タイプを簡単なチェックで見極められる!
- 「腰の性格」を知ることで、自分に合ったケアができる! 万人に効くストレッチは存在しません。必要なのは“自分に合う”セルフケアの選び方。
- 実際の問診&治療の様子を完全公開! まるで施術を受けているような感覚で読める、リアルな事例付き。
- 今すぐ始められる「腰痛予防の習慣」も掲載! 姿勢よりも「動かし方」がカギ。“90分に1度”の体の使い方を変えるだけで、腰は変わる。
こんな人におすすめ
- 慢性的な腰痛を根本から改善したい
- 整形外科や整体に通っても改善しなかった
- 自分に合ったセルフケア法が知りたい
- 将来の腰の不安を今からケアしたい
著者紹介
成田 崇矢(なりた・たかや)
桐蔭横浜大学大学院 スポーツ科学研究科 教授/理学療法士。
群馬大学医学部保健学科理学療法専攻を卒業後、筑波大学人間総合科学研究科博士前期課程修了、早稲田大学スポーツ科学研究科博士後期課程修了。病院や大学での臨床・教育を通じて、これまで数多くの腰痛患者と向き合ってきた。痛みの原因を的確に見極め、「自分でケアできる方法」をわかりやすく伝えることを大切にしている。全国から訪れる患者はもちろん、若手理学療法士の指導にも力を注いでいる。- 【主な著書】
- 成田崇矢の臨床 腰痛 (運動と医学の出版社刊)
- 脊柱理学療法マネジメント (メジカルビュー社刊)
- 秒速で体が柔らかくなる 5秒筋膜ゆらし (冬樹舎)
目次
- はじめに
- Chapter 1:実際の相談の様子(問診)をみてみよう
- 痛みの背景を理解する第一歩
- 相談① 仙腸関節に痛みがある方
- 相談② 筋・筋膜と椎間関節に痛みがある方
- Chapter 2:腰痛の原因を自分で探してみよう
- “その腰”、どう動くと怒り、どう扱うとご機嫌か?
- 腰のタイプは、大きく分けて4つ
- Chapter 3:自分の腰痛のセルフケアをしてみよう
- あなたの腰に合ったケアを見つけていく
- 椎間関節タイプのセルフケア
- 仙腸関節タイプのセルフケア
- 椎間板タイプのセルフケア
- 筋・筋膜タイプのセルフケア
- Chapter 4:腰痛を予防する習慣を身につけよう
- 「姿勢」よりも、「動かし方」で差がつく
- 「90分に1度」が背骨のリミット
- 胸椎の柔軟性をしっかり出す
- Chapter 5:腰痛のタイプを知り、もっと深く理解しよう
- あなたの腰痛に合わせた、最適な対策を選ぶために
- 椎間関節性腰痛の特徴
- 仙腸関節性腰痛の特徴
- 椎間板性腰痛の特徴
- 筋・筋膜性腰痛の特徴
- おわりに
ご購入はこちら
60代から差がつく 健康長寿のための からだのトリセツ~家族に迷惑をかけずに生き抜くエクササイズ習慣~
リハビリの先生が教える!
健康寿命を10年延ばす! 60歳からのからだのつくり方
人生100年時代を「ピンピンコロリ」で迎えるために必要な知識と実践方法
本書のポイント
- 理学療法士の専門的な視点から、健康寿命を延ばすために重要な、老化による運動機能の衰えとそのメカニズムを分かりやすく解説。
- 特に衰えやすい「柔軟性」「筋力」「バランス能力」に焦点を絞り、自分でできる効果的なセルフチェック方法と改善エクササイズを多数紹介。
- 「キーマッスル」と呼ばれる重要筋肉(大腰筋、大殿筋、大腿四頭筋)を効率的に鍛える方法を解説。
- 書籍と連動した動画があるので、エクササイズを正確に学ぶことができる。
- 毎日無理なく続けられる、日常生活に取り入れやすいエクササイズのヒントが満載。毎日5分でできるサーキットトレーニングも紹介。
書籍概要
この書籍は、現代日本において喫緊の課題となっている「健康寿命」をテーマにした一冊です。平均寿命が延びる一方で、健康寿命との間に約10年もの差があり、この期間に多くの人が介護を必要とし、医療費や介護費が国家財政を圧迫している現実を提示します。
著者は、健康管理を個人の問題だけでなく、家族や社会全体に対する「義務」として捉えるべきだと説き、特に60歳以降に顕著になる体の機能の衰えに焦点を当てています。運動機能の衰えは内臓や頭の機能の衰えとも関連しますが、自分自身の意思で最も維持しやすいのが運動機能であり、その維持が全身機能の維持につながると強調します。
本書では、老化によって特に衰えやすい「柔軟性」「筋力」「バランス能力」という3つの運動機能に絞り、そのメカニズムから具体的なセルフチェック方法、そして誰でも無理なく実践できる改善・予防エクササイズを詳しく解説します。体幹、股関節、ひざの柔軟性を高める方法、大腰筋、大殿筋、大腿四頭筋といった「キーマッスル」を効率的に鍛える方法、荷重の偏りを改善しバランス能力を高める方法などが、写真や動画(動画視聴方法の記載あり)を用いて分かりやすく紹介されています。
さらに、これらのエクササイズを日常生活に無理なく取り入れ、継続するための具体的なヒントも満載です。人生を「ロングゲーム」として捉え、今から体のメンテナンスを始めることの重要性を訴えかけ、一人でも多くの人が健康で、若く、生きがいを持った人生を送るための羅針盤となるでしょう。
著者紹介
園部 俊晴(そのべ としはる)
理学療法士
コンディション・ラボ 所長
運動と医学の出版社 代表取締役社長
関東労災病院リハビリテーション科で26年間勤務ののち、『コンディション・ラボ』を開業。
足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。
一般の人だけでなく、スポーツ選手にまで幅広く支持され、自身の治療院は約1年待ち。
多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛ける。
身体の運動連鎖や歩行に関する研究および文献多数。
専門家からの評価も高く、全国各地で講演活動を行う。
【主な著書】
- 「【痛み探偵シリーズ】ひざ痛探偵 (運動と医学の出版社)」
- 「園部式 足底筋膜炎 改善メソッド(彩図社)」
- 「園部式首の痛み改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「園部式歩行改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「園部式 脊柱管狭窄症 改善メソッド(彩図社)」
- 「園部式 ひざ痛 改善メソッド(彩図社)」
- 「つらいひざ痛が1分でよくなる! ひざ下リリース (わかさ出版)」
- 「お尻の痛み・しびれ 1分でよくなる 最新最強 自力克服大全(わかさ出版)」
- 「リハビリの先生が教える!健康寿命を10年延ばすからだのつくり方(運動と医学の出版社)」
など著書多数。
目次
- 第1章 人生はロングゲーム
- Topic1 健康寿命を延ばすことはすべての人の願い
- Topic2 60歳を超えると老化にも大きな差が出る!?
- Topic3 健康寿命と平均寿命の差は“10年”
- Topic4 ただ長生きするだけでは、良い晩年とは言えない
- Topic5 70歳以降の約 10年間で人生の半分の医療費がかかる!?
- Topic6 医療保険料が一律でなくなる時代がやってくる?
- Topic7 人生はロングゲーム
- Topic8 健康を維持することは、まずは運動機能を維持すること
- Topic9 衰えやすい運動機能とは
第2章 柔軟性 老いを遠ざける柔らかいからだ
- Topic1 なぜからだは硬くなるのか
- Topic2 からだが硬くなるとどうなる?
- Topic3 からだのどこが硬くなるのか
- Topic4 体幹の柔軟性を高めよう ―体幹が曲がるのを防ぐ方法―
- Topic5 股関節の柔軟性を高めよう ―股関節が曲がるのを防ぐ方法―
- Topic6 ひざの柔軟性を高めよう ―ひざが曲がるのを防ぐ方法―
第3章 筋力 いきいきと自由に動けるからだ
- Topic1 なぜ筋力が弱くなるのか?
- Topic2 どこを鍛えたら良いのか?
- Topic3 大腰筋の筋力低下を予防しよう
- Topic4 大殿筋の筋力低下を予防しよう
- Topic5 大腿四頭筋の筋力低下を予防しよう
第4章 バランス能力 安定してきれいに動けるからだ
- Topic1 なぜバランスが悪くなるのか?
- Topic2 バランスを悪くする 3つの要因
- Topic3 バランス能力が低下するとどうなる?
- Topic4 バランス能力を改善するには?
- Topic5 荷重の偏りを改善しよう!
第5章 健康寿命を延ばす日常のヒント 続けることで変化するからだ
- Topic1 エクササイズは継続がカギ
- Topic2 日常生活をエクササイズ化する
- Topic3 日常生活に取り入れるエクササイズのヒント
ご購入はこちら
下肢スポーツリハビリテーションー関東労災病院モデルー
—掲載症例—
■股関節疾患
- 股関節唇損傷
- ハムストリングス損傷・断裂
■膝関節疾患
- 膝前十字靭帯(ACL)損傷
- 膝内側側副靭帯(MCL)損傷
- 膝後十字靭帯(PCL)損傷
- 脛骨顆間隆起骨折
- 半月板損傷
- 膝蓋骨脱臼
- 膝蓋腱断裂
- 腸脛靱帯炎
- 鵞足炎
- 膝蓋腱炎
■足関節疾患
- 足関節外側靭帯損傷
- リスフラン靭帯損傷
- 腓骨筋腱脱臼
- アキレス腱断裂
- ジョーンズ骨折
—監修—
- 眞田 高起(関東労災病院スポーツ整形外科 部長)
—編集—
- 今屋 健(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 勝木 秀治(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
—著者一覧—
- 今屋 健(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 藤島 理恵子(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 田中 龍太(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 中山 誠一郎(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 志田 峻哉(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 橋本 昂史朗(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 海津 爽(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 大宅 一平(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 西見 太一(関東労災病院 中央リハビリテーション部)
- 要約図解資料PDF 本書の内容の一部をわかりやすく図解解説したPDFをダウンロードできます。本資料を読みながら書籍を読むことで、より全体概要をつかんだ状態で学ぶことができます。
▶▶こちらからダウンロードできます。ぜひ購入前に試し読みとして御覧ください
ご購入はこちら
マイナス10歳を手に入れる骨盤メンテ ~回転でととのう姿勢・柔軟ケア~
腰痛・猫背・ぽっこりお腹・反り腰・O脚・くびれのずれ….
骨盤メンテの最大のポイントは『歪み』ではなく『回転』⁉長年の腰痛や、姿勢の悪さに悩んでいませんか?多くの場合、その原因は「骨盤の歪み」ではなく、「骨盤の回転」であることをご存知ですか? 本書は、理学療法士として15年以上の臨床経験を持つ著者、土屋元明(動きのこだわりテーション)が、これまでの常識を覆し、「骨盤の回転」という新たな視点から、マイナス10歳の体力・姿勢を手に入れるためのセルフケアを提案する画期的な一冊です。 「骨盤の回転」で姿勢が変わる!
■「骨盤の回転」で姿勢が変わる!
本書では、骨盤がどのように回転しているかによって、反り腰、猫背、O脚、ぽっこりお腹など、様々な姿勢の問題が生じることを、豊富な図解を用いてわかりやすく解説。さらに、それぞれのタイプに合わせた、効果的かつ簡単に実践できるセルフケアを具体的に紹介しています。 体の軸となる骨盤をととのえ、全身の柔軟性を高めることで、腰痛や姿勢の悪さなどの悩みを根本から解決へと導きます。 骨盤メンテでご自身の体力を密かにチェック!
本書では、読者が自分の体の状態を客観的に把握できるよう、 10点満点の採点方式によるセルフチェックシートを掲載。 「反る・曲げる」「ねじる・まわす」「立ち上がり」という3つのカテゴリーで、体の柔軟性と筋力をチェックして問題点を把握することができます。
■骨盤メンテでご自身の体力を密かにチェック!
本書では、読者が自分の体の状態を客観的に把握できるよう、 10点満点の採点方式によるセルフチェックシートを掲載。 「反る・曲げる」「ねじる・まわす」「立ち上がり」という3つのカテゴリーで、体の柔軟性と筋力をチェックして問題点を把握することができます。
■著者
土屋 元明(つちや げんめい)
理学療法士インソールとリハビリの専門院「動きのこだわりテーション」にて、痛みなどを抱える人の体にかかるストレスを改善しながら、回復方向へ向かう暮らしやセルフケアを提案している。「運動の質=人生の質」をモットーに、健康寿命延伸のために、医学書、雑誌、TV、講演など幅広く活躍中。 著書に、『ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る─1日5分から始める超簡単ひざトレーニング』(方丈社)、『不調と痛みが消える! 10秒筋膜ほぐし』(主婦の友社)ほか多数。
■目次
- はじめに 骨盤の歪みの正体って何?
- 第1章 骨盤は何のためにある?
- 骨盤は仙骨と寛骨で構成されている
- 骨盤の回転で姿勢は決まる
- 腰・股関節が骨盤の回転を支えている
- 反り腰をケアする
- ぽっこりお腹をケアする
- 猫背をケアする
- O脚をケアする
- くびれラインのくずれをケアする
- 第2章 骨盤から体をととのえる
- 股関節や胸郭が体をねじる主体
- 「ケンダルの姿勢分類」からわかること
- ニュートラルな姿勢がもたらすメリット
- スウェーバックは猫背になりがち
- カイホロードシスも猫背になりやすい
- ロードシスには腰を丸めるケアが必要
- フラットバックは腰の柔軟性がなくなる
- 骨盤と下半身はどうつながっている?
- 体全体をととのえる六つの骨盤メンテ
- ひじ上げメンテのやり方
- 座って前屈するメンテのやり方
- 腕うしろ伸ばしメンテのやり方
- 四つ這い反らしメンテのやり方
- 骨盤倒しメンテのやり方
- ゆりかご立ちメンテのやり方
- 第3章 腰痛に効く座り方・立ち方・歩き方
- 腰痛に効く座り方=軸座りケア
- 腰痛に効く立ち方=頭、骨盤、足をそろえる
- 腰痛に効く歩き方=腕をふって歩く
- 付章 仙腸関節の痛みはこれでわかる
- 痛みがあれば専門家のサポートが必要
- 仙腸関節の痛みは自分で確認できる
- 仙腸関節の痛みをセルフチェック
- おわりに 骨盤の歪みの多くは矯正しなくてもいい
ご購入はこちら
園部俊晴の臨床『徒手療法ガイドブック』腰部・殿部・股関節・大腿編
- 慢性痛を引き起こす原因となる「滑走性」と「伸張性」の重要性について解説。
- 痛みの評価と治療に役立つ「第3水準の評価」について詳しく解説
- 腰部、殿部、股関節、大腿の各部位に対する具体的な徒手療法テクニックを、豊富な写真とわかりやすい解説で紹介。
- 多裂筋、腸肋筋、梨状筋、大腿筋膜張筋など、主要な筋肉へのアプローチ方法を網羅。
- 坐骨神経、大腿神経など、神経に対するアプローチ方法も解説。
- 第 Ⅰ 部 基本が分かれば誰でもできる!
- 第1章 滑走性と伸張性のテクニックを手に入れる重要性
- 慢性痛はどうして起こるのか?
- 慢性痛を考える際の留意点
- 慢性痛には常に滑走性と伸張性の改善が鍵を握っている
- 痛みを生じさせる組織とは
- 第2章 最高のセラピストになるための絶対条件「第3水準の評価」とは
- よく見受ける事例
- 運動器疾患の治療に必要な流れ
- 第3水準の評価
- 第3水準の評価までのプロセスを実践するために
- 第1章 滑走性と伸張性のテクニックを手に入れる重要性
- 第 Ⅱ 部 滑走性・伸張性改善テクニックの実際
- 第1章 腰部への滑走性・伸張性改善テクニック
- 多裂筋
- 腸肋筋
- 腰方形筋
- 椎間関節
- 仙腸関節
- 上殿皮神経
- 第2章 殿部への滑走性・伸張性改善テクニック
- 坐骨神経
- 上殿神経
- 後大腿皮神経
- 大殿筋
- 梨状筋
- 寛骨三筋
- 大腿方形筋
- 中殿筋
- 小殿筋
- 転子部滑液包
- 第3章 股関節・大腿への滑走性・伸張性改善テクニック
- 腸腰筋
- 大腿神経
- 大腿筋膜張筋
- 縫工筋
- 大腿直筋
- 大腿直筋反回頭
- 長内転筋
- 薄筋
- 内側広筋・外側広筋
- 伏在神経
- 坐骨神経(膝窩部)
- 内・外側ハムストリングス
- 第1章 腰部への滑走性・伸張性改善テクニック
要約図解資料PDF
本書の内容の一部をわかりやすく図解解説したPDFをダウンロードできます。本資料を読みながら書籍を読むことで、より全体概要をつかんだ状態で学ぶことができます。
▶▶こちらからダウンロードできます。ぜひ購入前に試し読みとして御覧ください
ご購入はこちら
理学療法超音波学 vol.2
- 好評を博した前作vol.1に続き、2023年3月開催された第4回日本運動器理学療法超音波フォーラムで注目を集めたトピックスを、豊富な図表と動画で解説!
- 「神経・痛み、教育」「手指関節」「膝・大腿」「肩・肘、胸郭」の4つに関する16タイトルを収載。
- 超音波画像による評価バリエーションを増やすことにより、痛みを発している原因へのアプローチの“解像度”が大幅に向上する。
Chapter 1: 神経・痛み、教育
- 末梢神経を基軸としたサイレント・マニピュレーション後の運動療法から生活指導まで座位痛を可視化する
- ドケルバン病の圧痛部位から考える理学療法の展開 ―PC test 変法を用いての検討―
- 理学療法教育におけるエコーの活用
- 札幌医科大学超音波グループの活動報告 ―4年間の歩み―
Chapter 2: 手指関節
- ばね指の様々な病態とリハビリ
- ばね指に対するA1プーリーストレッチの効果検証
Chapter 3: 膝・大腿
- エコーを用いた内側半月板後根断裂における内側半月板逸脱量の観察 ―内側半月板後根断裂の治療選択からリハビリまで ―
- ハムストリングス各筋の伸張に伴うストレイン-スティフネス関係
- 後十字靭帯損傷膝における後方不安定性の評価
- 膝前面痛に対する理学療法の評価と治療方略
Chapter 4: 肩・肘、胸郭
- 内側型野球肘治療の再考 ― 投球相による痛みの違いに着目して ―
- 野球選手のMCL損傷に対するPRP療法における血流評価
- 投球障害肩に対する私たちの超音波エコー研究
- 肩腱板断裂患者における肩甲上腕関節の動的アライメントの特徴
- 胸郭可動域練習が肋間筋スティフネスに与える影響
【要約図解資料PDF】理学療法超音波学 vol.2
本書の内容の一部をわかりやすく図解解説したPDFをダウンロードできます。本資料を読みながら書籍を読むことで、より超音波エコーの臨床応用のヒントを学ぶことができます。
[TOPIX]
- 座位痛を可視化する
- 膝前面痛に対する理学療法の評価と治療方略
▶▶こちらからダウンロードできます。ぜひ購入前に試し読みとして御覧ください
ご購入はこちら
園部式脚の痛み・しびれ改善メソッド

腰だけが原因じゃない!—知られざる脚の痛みの真実とは?
医者任せにしない!年齢のせいにしない!
手術を考える前にあなた自身で痛みの原因を見つける方法を人気治療家がわかりやすく解説。
●つらい脚の痛み・しびれは◯◯が原因?プロスポーツ選手や著名人が多数 来院する一流治療家がセルフケアを大公開
数多くの著名人やプロスポーツ選手が集まる理学療法士が考案した【園部式 脚の痛み・しびれ改善メソッド】は、【椎間板ヘルニア】【脊柱管狭窄症】【坐骨神経痛】と診断された全ての人の為のセルフケア。30年以上の経験から導き出された痛みとしびれを引き起こす【3つの原因】を自分で特定し、原因別の簡単ケアの方法を公開しています。
【この書籍のポイント】
- 『椎間板ヘルニア』『脊柱管狭窄症』『坐骨神経痛』と診断された人の為のセルフケアの方法を紹介
- 数多くの著名人やプロスポーツ選手を担当している超実力派セラピストが伝授
- 運動が苦手でも大丈夫!わかりやすい写真やQR動画でわかりやすくケアを学べる
- しびれや痛みの本当の原因を自分で見つけて、適切なケア方法を学べる
●YouTubeで大好評!有名プロスポーツ選手が多数来院する実力派セラピストが実際に指導しているセルフケアを大公開
本書の著者の園部俊晴は関東労災病院リハビリテーション科で26年間勤務ののち、『コンディション・ラボ』を開業。足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。一般の人だけでなく、プロのスポーツ選手にまで幅広く支持され、自身の治療院は約1年待ち。多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛けています。
また、自身がプロデュースするYouTubeチャンネル『コンディション・ラボ』では毎週、体の悩みを解決する方法を紹介しており、一般の方以外にも、プロのトレーナーやセラピストにも信頼されているチャンネルとなっています。
本書はYouTubeでも好評だった『脚のしびれと痛みに対するケア』というテーマを、だれでも簡単にできるようにアレンジした内容を紹介しています。
■YouTubeリンク
https://youtu.be/gxQ0bPPNEGA
■治療院HP
https://conditionlabo.com/
■著者
園部 俊晴(そのべ としはる)
理学療法士
コンディション・ラボ 所長
運動と医学の出版社 代表取締役社長
関東労災病院リハビリテーション科で26年間勤務ののち、『コンディション・ラボ』を開業。足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。一般の人だけでなく、スポーツ選手にまで幅広く支持され、自身の治療院は約1年待ち。多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛ける。身体の運動連鎖や歩行に関する研究および文献多数。著書多数。専門家からの評価も高く、全国各地で講演活動を行う。
- 【主な著書】
- 「園部式歩行改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「園部式 脊柱管狭窄症 改善メソッド(彩図社)」
- 「園部式 ひざ痛 改善メソッド(彩図社)」
- 「つらいひざ痛が1分でよくなる! ひざ下リリース (わかさ出版)」
- 「お尻の痛み・しびれ 1分でよくなる 最新最強 自力克服大全(わかさ出版)」
- 「リハビリの先生が教える!健康寿命を10年延ばすからだのつくり方(運動と医学の出版社)」など著書多数
■目次
- 第1章 脚の痛みやしびれの本当の原因とは?
- 第2章 原因部位発見! セルフチェック法
- 第3章 脚の痛みやしびれの原因別セルフケア
- 第4章 痛みやしびれを予防するデイリーケア
ご購入はこちら
痛み探偵シリーズ ひざ痛探偵

ひざ痛の謎はすべて解けた!
4つの犯人(原因部位)を名探偵ソノベが推理!
犯人(原因部位)別の解決法を漫画でわかりやすく解説!
■著者
園部 俊晴(そのべ としはる)
理学療法士
コンディション・ラボ 所長
運動と医学の出版社 代表取締役社長
関東労災病院リハビリテーション科で26年間勤務ののち、『コンディション・ラボ』を開業。足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。一般の人だけでなく、スポーツ選手にまで幅広く支持され、自身の治療院は約1年待ち。多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛ける。身体の運動連鎖や歩行に関する研究および文献多数。著書多数。専門家からの評価も高く、全国各地で講演活動を行う。
- 【主な著書】
- 「園部式歩行改善メソッド(運動と医学の出版社)」
- 「園部式 脊柱管狭窄症 改善メソッド(彩図社)」
- 「園部式 ひざ痛 改善メソッド(彩図社)」
- 「つらいひざ痛が1分でよくなる! ひざ下リリース (わかさ出版)」
- 「お尻の痛み・しびれ 1分でよくなる 最新最強 自力克服大全(わかさ出版)」
- 「リハビリの先生が教える!健康寿命を10年延ばすからだのつくり方(運動と医学の出版社)」など著書多数
■目次
- 第1章 痛みの犯人(原因部位)を探せ!
- 第2章 4つの原因別 今すぐできる痛み改善ケア
- 第3章 ひざを痛めない毎日習慣
- 第4章 ひざ痛を元から治す! 毎日簡単エクササイズ
1日3分自触習慣!触診ドリル 上肢・頚部編

触診ドリル。
それはペンもノートもいらない、究極の学習法。
多くのセラピストが『 触診は大事 』と アドバイスを受けたことがあるはずです。
しかし、いざ触診の勉強を始めようとしても、
『練習相手がいない …』
『場所と時間の確保が難しい …』
などの理由で、挫折した人は多いはず。
そこで、 これらの問題を解決する究極の学習法を考案しました。
その名は『自触(じしょく)』です。
自触とは、『 “自”分の身体を“触”診する学習法』です。
自触は触れる感触・触れられる感触を同時に体感できるため、他人に対して触診するよりも効果的に学習できます。
練習相手も場所も必要ないため、1 日 3 分、自触を続ければ、1 ヶ月後にはあなたの触診スキルは大幅に向上するでしょう。 どんなに知識があっても、どんなに臨床推論ができても、最後に頼りになるのは あなた自身の” 手 “です。
必要なのは、あなたの手と、この本だけ。
さあ身につけましょう、 信頼できる触診スキルを。
POINT①
いつでもどこでも効率よく練習できる
自触は1人でどこででも行うことができます。また、他人を触れるより、自分自身を触れるほうが、対象が良く分かる為、効率的に練習できます。自分自身を触れるのに遠慮は要りません。どんどん触れていきましょう。
POINT②
専門用語を使わない分かりやすい文章構成
本書では、可能な限り解剖学用語や運動学用語を知らないでも肢位や運動が理解できるような文章構成にしています。そのため、初学者でもイメージしやすく、楽しく読めるように工夫しています。
POINT③
臨床応用につながる知識も多数掲載
本書では各部位の初めに、対象部位の機能解剖学と臨床との接点についての解説があります。そのため、習得した触診技術をどのように臨床に応用するのかをイメージしながら練習できるので、効果的に学習できます。
———
目次
———
第1章:骨
1.頭部・頚部
① 頭部
- 乳様突起
- 外後頭隆起
- 上項線
- 下項線
② 頚部
- 第1 頚椎横突起
- 第2 頚椎棘突起
- 第7 頚椎棘突起
2.肩甲帯・胸郭
① 肩甲骨
- 肩甲骨上角
- 肩甲骨下角
② 鎖骨
- 鎖骨骨幹部
- 胸鎖関節
- 肩鎖関節
③ 胸骨・肋骨
- 頚切痕
- 胸骨角
- 胸骨柄
- 胸骨体
- 剣状突起
- 肋骨(真肋)
- 第1 肋骨
- 第2 肋骨
- 第11 肋骨
- 第12 肋骨
3.肩・上腕
① 肩甲骨
- 肩峰
- 肩甲棘
- 烏口突起
② 上腕骨
- 上腕骨頭
- 上腕骨大結節
- 大結節上面
- 大結節中面
- 大結節下面
- 上腕骨小結節
- 結節間溝
- 三角筋粗面
- 橈骨神経溝
4.肘・前腕
① 上腕骨
- 上腕骨滑車
- 上腕骨内側上顆
- 上腕骨外側上顆
- 尺骨神経溝
- 上腕骨小頭
② 橈骨
- 橈骨頭
- 腕橈関節
- 橈骨粗面
③ 尺骨
- 肘頭
- 肘頭窩
5.手関節・手指
① 手関節
- 橈骨茎状突起
- 尺骨頭
- 尺骨茎状突起
- リスター結節
② 手根骨
- 豆状骨
- 三角骨
- 月状骨
- 舟状骨
- 舟状骨結節
- 大菱形骨
- 大菱形骨(裏技)
- 小菱形骨
- 有頭骨
- 有鉤骨
- 有鉤骨鉤
③ 指骨
- 中手骨頭
- 中手骨骨幹部
- 基節骨
- 中節骨
- 末節骨
④ 指関節
- 母指CM 関節
- 母指MP 関節
- 母指IP 関節
- 示指MP 関節
- 示指PIP 関節
- 示指DIP 関節
第2章:軟部組織(筋・靭帯・その他)
1.頭部・頚部
① 斜角筋群
- 前斜角筋
- 前斜角筋(裏技)
- 中斜角筋
- 中斜角筋(裏技)
2.肩甲骨・胸郭
① 前方
- 前胸鎖靭帯
- 胸鎖乳突筋
- 小胸筋
- 前鋸筋
② 後方
- 僧帽筋(上部線維)
- 大菱形筋
- 小菱形筋
3.肩・上腕
① 肩関節複合体に関連する靭帯
- 肩鎖靭帯
- 烏口鎖骨靭帯(菱形靭帯)
- 烏口鎖骨靭帯(円錐靭帯)
- 烏口肩峰靭帯
- 烏口上腕靭帯
② 肩関節複合体に関連する筋(前方)
- 大胸筋鎖骨部
- 大胸筋胸肋部
- 大胸筋腹部
- 三角筋前部線維
- 肩甲下筋
- 肩甲下筋停止部
- 烏口腕筋
- 烏口腕筋(裏技)
- 上腕二頭筋筋腹
- 上腕二頭筋長頭(近位)
- 上腕二頭筋短頭(近位)
- 上腕二頭筋腱(遠位)
- 上腕筋(外側縁)
- 上腕筋(内側縁)
③ 肩関節複合体に関連する筋(後方)
- 広背筋
- 三角筋中部線維
- 三角筋後部線維
- 棘上筋
- 棘下筋
- 小円筋
- 大円筋
- 上腕三頭筋内側頭
- 上腕三頭筋外側頭
- 上腕三頭筋長頭
4.肘・前腕
① 前腕屈筋と肘内側の靭帯
- 内側側副靭帯
- 円回内筋
- 橈側手根屈筋
- 橈側手根屈筋(裏技)
- 長掌筋
- 尺側手根屈筋
- 尺側手根屈筋(裏技)
- 長母指屈筋
- 方形回内筋
② 前腕伸筋と肘外側の靭帯
- 橈骨輪状靭帯
- 外側側副靭帯
- 尺側手根伸筋
- 腕橈骨筋
- 長橈側手根伸筋
- 短橈側手根伸筋
- 回外筋
- 肘筋
③ 手指を動かす前腕の筋
- 浅指屈筋
- 浅指屈筋腱
- 深指屈筋(環指・小指)
- 深指屈筋腱
- 総指伸筋
- 示指伸筋
- 小指伸筋
- 長母指伸筋
- 短母指伸筋
- 長母指外転筋
5.手・手指
① 手掌で触れる手内筋
- 屈筋支帯
- 長母指屈筋腱
- 母指内転筋横頭
- 母指内転筋斜頭
- 短母指外転筋
- 短母指屈筋
- 母指対立筋
- 小指外転筋
- 短小指屈筋
- 小指対立筋
② 手背で触れる指伸筋と腱
- 総指伸筋腱
- 示指伸筋腱
- 小指伸筋腱
- 腱間連結
- 短母指伸筋腱
- 長母指外転筋腱
- スナッフボックス(嗅ぎタバコ窩)
- 背側骨間筋(示指)
- 掌側骨間筋(示指)
- 虫様筋Ⅱ(示指)
6.神経・動脈
① 頭部・頚部
- 腕神経叢(の一部)
- 総頚動脈
② 肩・上腕
- 腋窩神経(QLS)
- 筋皮神経
- 橈骨神経(上腕)
- 上腕動脈
③ 肘・前腕
- 橈骨神経(前腕)
- 尺骨神経(肘)
- Osborne’s band
- 肘部管
- 正中神経(近位)
④ 手関節・手指
- 尺骨神経(遠位)
- 正中神経(手根部)
- 橈骨動脈
園部式首の痛み改善メソッド

『3年も悩んだ首の痛みがあっけなく改善した!』
数多くの著名人・プロアスリートを治療している治療家、
園部俊晴が首の悩みの4つの原因と解決方法を紹介!
■首の痛みの原因組織は4つある
「首の痛みの原因組織」は90%が、次の4つにあてはまります。
- 皮膚(浅層筋膜)
- 筋膜(深層筋膜)
- 筋
- 椎間関節(関節包・靭帯)
こう説明されると、「私のこのつらい痛みの原因が、たった4つのどれかなの?」と思う方もいるかもしれません。とくに、「痛みの原因は皮膚にあった」と聞かされると、驚く方がほとんどです。ですが、これが痛みの原因組織であるケースは意外と多いのです。皮膚といっても、皮膚の表面ではなく、正しくは「浅層筋膜」のことです。ただ、一般的には皮膚と表現したほうがわかりやすいので、本書では「皮膚」としています。
そして、その下にある筋膜(深層筋膜)や筋が原因の方も結構います。さらに、椎間関節を入れると、痛みの90%がこの4つに収まります。というのも、この4つの組織にアプローチをすると、その場で首の痛みが明らかに改善する患者さんが多いからです。ただ、ここで1つ、お断りしておきたいことがあります。最後にあげた椎間関節ですが、これは患者さんが自分でチェックしたり治療したりすることができません。
ですから本書では、それ以外の3つの組織(皮膚、筋膜、筋)について、自分でチェックする方法と改善方法をお教えしていきます。「せっかくなら、椎間関節についても教えてくれればいいのに」と思う方もいるかもしれません。でも、3つが原因となるケースが多いので、それを知るだけでも、あなたがずっと悩んでいる首の痛みが解消する確率は、ぐっと高くなるはずです。
■こんな人にオススメ
- 首の痛みに長年悩んでいる。
- 「頸椎症」、「頸椎椎間板ヘルニア」などの首の診断名を受けた人。
- いろんな病院や整体院に言ったが症状が改善しなかった人。
- 首の痛みの本当の原因を知りたい人
———
目次
———
- 【Chapter1 首の痛みの本当の原因って何?】
- 病名は痛みの真の原因を表すものではない
- 「首の痛み」とはどこを指すのか
- 首の痛みの原因組織は4つある
- 痛みの原因がレントゲンに写らない理由
- 【Chapter2 首の痛みのセルフチェック │ 皮膚】
- 倒すべき敵の1つは、「皮膚」
- 《体験談》3年も悩んだ首の痛みがあっけなく改善した!
- 痛みの種類と範囲
- セルフチェックの手順
- 皮膚による首の痛みのセルフチェック方法
- 園芸用のゴム手袋を用いるメリット
- 【Chapter3 首の痛みのセルフチェック │ 筋膜】
- 《体験談》「反る」と首が痛む原因は筋膜にあった
- 痛みの範囲が広く、場所がはっきりしない
- セルフチェックの手順
- 筋膜による首の痛みのセルフチェック方法
- 【Chapter4 首の痛みのセルフチェック │ 筋】
- 痛みの場所をはっきり言えるときは、筋肉が原因かも
- 痛みを起こしやすいのはどの筋肉?
- セルフチェックの手順
- 後頭下筋群による首の痛みのセルフチェック方法
- 多裂筋と半棘筋による首の痛みのセルフチェック方法
- 僧帽筋と肩甲挙筋による首の痛みのチェック方法
- ストレートネックの問題点
- 【Chapter5 首の痛みのセルフケア】
- 痛みの原因組織が皮膚の場合のセルフケア
- 痛みの原因組織が筋膜の場合のセルフケア
- 痛みの原因組織が筋の場合のセルフケア
理学療法超音波学 vol.1

Chapter 1: 肩・股関節
- 肩3rd肢位の内旋における上腕骨頭の動態評価(鳴尾 龍一郎)
- 末梢神経を基軸に考える肩関節拘縮治療(中川 宏樹)
- 投球障害肩に対する3方向Scapular Assistance Testと超音波(小林 弘幸)
- 関節運動に伴う股関節内転筋群の力学的な特性評価(加藤 拓也/谷口 圭吾)
- 超音波で見る股関節不安定性とその意義(河合 誠)
Chapter 2: 組織弾性
- 膝関節屈曲角が膝蓋腱の組織弾性に及ぼす影響(三谷 保弘)
- 鏡視下Bankart修復術後肩における烏口上腕靭帯の組織弾性 ―超音波診断装置を用いた経時的評価と外旋可動域の関係―(麻田 昌彦)
- 肩内旋運動中の肩後方軟部組織の弾性変化(相馬 章吾)
- 変形性膝関節症における膝蓋下脂肪体の硬度計測と組織酸素計測(堤 真大/工藤 慎太郎)
Chapter 3: 神経・血管
- いわゆる坐骨神経痛に対する理学療法評価―大腰筋の深層を科学する―(岡本 光司)
- 腕神経叢牽引刺激に伴う腋窩動脈血流速度変化の検討―臨床応用を交えて―(二村 涼)
- 末梢神経から考える肩肘の運動機能障害―肘内側部痛を有する尺骨神経障害―(河端 将司/宮武 和馬)
- 頚髄血行動態と不良姿勢における関係(井上 彰/小林 凌)
Chapter 4: 評価・リハビリテーション
- ジュニア期バスケットボール選手に対する超音波を用いたメディカルチェック―OBA医科学委員会スポーツ外傷・障害予防事業―(沼澤 俊)
- トラッキング手法を用いた動態解析評価(二村 英憲)
- 手の狭窄性腱鞘炎に対してエコーを活用したリハビリテーション(杉浦 史郎)
- エコーだからこそ見える、体幹機能評価―体幹筋厚と下肢障害の関係―(村本 勇貴)
【要約図解資料PDF】理学療法超音波学 vol.1
本書の内容の一部をわかりやすく図解解説したPDFをダウンロードできます。本資料を読みながら書籍を読むことで、より超音波エコーの臨床応用のヒントを学ぶことができます。
[TOPIX]
- 末梢神経を基軸に考える肩関節拘縮治療
- いわゆる坐骨神経痛に対する理学療法評価
- 腕神経叢牽引刺激に伴う腋窩動脈血流速度変化の検討
- 末梢神経から考える肩肘の運動機能障害
肩関節の極意 痛み編

肩関節治療のスペシャリスト千葉慎一の待望の単著が発売! “極意“シリーズ第1弾のテーマは『痛み』。 肩関節痛の痛みを発生させる4つの部位にフォーカスを当てて、それぞれの評価と治療の極意を余すことなく公開する。
POINT①
肩関節の痛みを発生させる『4つの関節』について徹底解説
肩関節の痛みの多くが、肩甲上腕関節、第2肩関節、結節間溝、肩鎖関節の4つの部位に集約されています。本書ではそれぞれの病態や、原因を特定するための評価・鑑別方法や治療方法を分かりやすく説明しています。
POINT②
『神経由来の痛み』についても深堀り解説
実際の臨床では、先述4つの関節以外の問題で肩の痛みを訴える症例も存在します。こうした症例の共通点として多いのが、痛みが比較的広範囲に存在していることや、動作によっては痛みの部位が異なったりすることが挙げられます。こうした場合は、まず「神経由来の痛み」が関与を疑います。本書の最終章ではこの『神経由来の痛み』について、各病態の評価・鑑別方法や治療方法を分かりやすく説明しています。
POINT③
書籍内のQRから実技映像が観れる
本書には著者による21本の解説動画を視聴できるQRコードが多数用意されています。文章ではイメージしづらいニュアンスを映像で視覚的に理解することができます。
一流の臨床思考

いつの時代も、どの業界でも、最短で上達できる方法には共通点がある。
それは、『一流から学ぶ』こと。
しかし、講習会に参加したり、臨床見学をしても、「臨床力が劇的に向上した」という人は少ない。
それもそのはず。
まず一流から学ぶべきことは“技術”でなく、“思考”に他ならないからだ。
臨床における“思考”とは『評価→アプローチ→効果判定』までの“点”と“点”を繋ぐ重要なプロセスだ。
一流の臨床家ほど、このプロセスが卓越している。
彼らは評価や効果判定によって、論理的に情報を整理し、アプローチの優先順位を導き出すことが当たり前のように行えている。
本書はそんな一流の臨床思考を学べるように、日本を代表する3名の臨床家が執筆している。
彼らの臨床思考を覗き見ることで、“知識”が“知恵”になり、その“知恵”が“思考”の積み重ねによって、一流の技術へ昇華する。
磨き続けた“思考”は武器になる。
さあ、磨こう。一流になるための思考を。
POINT①
Q&A形式でわかりやすい
本書はよくある臨床の疑問を3名の一流臨床家が1つ1つ丁寧に解説する構成になっています。会話の中から一流の臨床家の思考過程を覗けるような文体になっている為、本書で学んだ知識が臨床現場で応用し易いように工夫されています。
POINT②
3名の一流臨床家が下肢・腰・肩を徹底解説
今回執筆している3名は全国トップクラスの実力を持ち、講演でも人気の臨床家です。そんな3名がそれぞれ担当してる『下肢疾患』、『腰部疾患』、『肩関節疾患』についての様々な疑問について、わかりやすく徹底解説してくれます。
■園部 俊晴(理学療法士/コンディション・ラボ)
入谷誠の一番弟子。足・膝・股関節など、整形外科領域の下肢障害の治療を専門としている。一般からスポーツ選手まで幅広く支持され、、多くの一流アスリートや著名人などの治療も多く手掛ける。身体の運動連鎖や歩行に関する研究および文献多数。著書多数。新聞、雑誌、テレビなどのメディアにも多く取り上げられる。また、運動連鎖を応用した治療概念は、専門家からの評価も高く全国各地で講演活動を行う。
■赤羽根 良和(理学療法士/さとう整形外科)
1999年に平成医療専門学院を卒業後、理学療法士免許を取得、吉田整形外科に入職する。2009年よりさとう整形外科で勤務し、整形外科リハビリテーション学会の理事も務める。整形外科領域での治療を専門とし、本書の監修であり恩師である林典雄から拘縮理論を学んだことで理学療法士としての頭角を現す。拘縮理論を広く一般化すべく、自ら「ICA理論」を考案。臨床現場では圧倒的な治療成績を出しながら積極的に講演活動を行い、赤羽根良和から指導を受けたいというセラピストが後を絶たない。
■千葉 慎一(理学療法士/ウェルケアわきた整形外科)
1995年に読売ジャイアンツで専属トレーナーを務めた理学療法士。東京2020オリンピックでは「野球競技理学療法サービスコーディネーター」、「野球競技会場チーフ理学療法士」として活躍。肩関節疾患のリハビリテーションを専門とし、一般人からスポーツ選手まで幅広く肩関節疾患の治療に関わる。肩関節についての執筆・研究などを行う傍ら、全国で講演を行っている肩関節のスペシャリスト。
POINT③
書籍内のQRから実技映像が観れる
本書には各種実技の動画を視聴できるQRコードが多数用意されているため、多彩な手技やエッセンスが分かりやすくなっています。
ご購入はこちら
膝関節拘縮の評価と運動療法 改訂版

本書は、2020年に出版された『膝関節拘縮の評価と運動療法』の改訂版です。
シリーズ5万部を越えている『拘縮』シリーズでも特に人気の本書に128本の実技映像を追加し、読者がより効果的に学ぶことができるようになっています。
また、本書では膝関節拘縮に関して大きく分けて、機能解剖、屈曲制限、伸展制限の三本柱でまとめてあり、膝関節拘縮を軟部組織である皮膚・皮下組織、筋、靭帯、関節包に分けてとらえる評価、腫脹浮腫管理、疼痛の配慮、可動域の優先順位、筋収縮・筋力強化方法、関節可動域制限の病態を示しながら、具体的な運動療法が記載されています。
さらに、運動器リハビリテーションの現場で最も遭遇することが多いTKA(人工膝関節全置換術)などを中心に術前・術後アプローチが網羅されています。
128本の実技動画でさらにわかりやすく
QRコードを読み取ることで、本書で紹介された運動療法を実際に実践している著者の解説映像を128本視聴することができます。本書を読むことで、膝関節拘縮の適切な評価と効果的な運動療法の実際を学ぶことができます。前作を読んだ読者はもちろん、新たに知見をブラッシュアップしたい方にもオススメの書籍となっています。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=178967695
1日3分自触習慣!触診ドリル 下肢・体幹編
触診ドリル。
それはペンもノートもいらない、
究極の学習法。
多くのセラピストが『 触診は大事 』と アドバイスを受けたことがあるはずです。
しかし、いざ触診の勉強を始めようとしても、
『練習相手がいない …』
『場所と時間の確保が難しい …』
などの理由で、挫折した人は多いはず。
そこで、 これらの問題を解決する究極の学習法を考案しました。
その名は『自触(じしょく)』です。
自触とは、
『 “自”分の身体を“触”診する学習法』です。
自触は触れる感触・触れられる感触を同時に体感できるため、他人に対して触診するよりも効果的に学習できます。
練習相手も場所も必要ないため、1 日 3 分、自触を続ければ、1 ヶ月後にはあなたの触診スキルは大幅に向上するでしょう。 どんなに知識があっても、
どんなに臨床推論ができても、
最後に頼りになるのは あなた自身の” 手 “です。
必要なのは、あなたの手と、この本だけ。
さあ身につけましょう、 信頼できる触診スキルを。
POINT①
いつでもどこでも効率よく練習できる
自触は1人でどこででも行うことができます。また、他人を触れるより、自分自身を触れるほうが、対象が良く分かる為、効率的に練習できます。自分自身を触れるのに遠慮は要りません。どんどん触れていきましょう。
POINT②
専門用語を使わない分かりやすい文章構成
本書では、可能な限り解剖学用語や運動学用語を知らないでも肢位や運動が理解できるような文章構成にしています。そのため、初学者でもイメージしやすく、楽しく読めるように工夫しています。
POINT③
臨床応用につながる知識も多数掲載
本書では各部位の初めに、対象部位の機能解剖学と臨床との接点についての解説があります。そのため、習得した触診技術をどのように臨床に応用するのかをイメージしながら練習できるので、効果的に学習できます。
臨床に役立つPNF

今こそ学べ、時代を超えた原理と原則
図表760以上、QR動画50以上の圧倒的ボリュームで治療効果をさらに拡張させろ!
セラピストに世界的に広まった手技としては、最も歴史の長い手技の1つ、PNF。現在では、トレーナーや理学療法士、整形外科医などによって世界中で広く用いられている。その適応範囲も広く、筋の機能向上、スポーツパフォーマンスの向上、麻痺性疾患の動作の改善、運動器疾患の動作の改善などに効果があり、様々な分野で活用されている。この書籍では日本に数名しかいない国際PNF協会アドバンスインストラクターが10日間のコースで教えている内容を余すことなく解説している。圧倒的な量の解説写真と,各種実技の動画を視聴できるQRコードが多数用意されているため、多彩な手技やエッセンスが分かりやすくなっている。
POINT①
アプローチ効果を最大化させる原則を多数紹介
アプローチ効果を最大化させる5つの法則や、運動学習・制御理論に基づいたアプローチの原則を学ぶことができる。
POINT②
10日間の国際コースの内容を1冊に凝縮!
10日間(75時間)の国際PNF協会(IPNFA)認定ベーシックコースの内容を1冊に凝縮。
POINT③
実際の症例へのアプローチを紹介。学んだ知識の応用を学べる!
運動器疾患・中枢神経疾患・スポーツパフォーマンスへの3例の実例紹介。学んだ知識の応用を学べる。
POINT④
嚥下・呼吸障害、顔面神経麻痺など幅広い症例の対処法を紹介!
嚥下障害、呼吸障害、顔面神経麻痺に対するアプローチも紹介!幅広い現場のセラピストに対応した技術を網羅。
ご購入はこちら
関節可動域

▶「各関節の制限因子」「基礎知識」「運動器疾患」「中枢神経疾患」の4つのテーマを各分野のエキスパートが深掘り!
▶圧巻の30項目の知識を学び、“臨床現場に活かせる“関節可動域の知識を習得!
理学療法を生業とする我々にとって、“関節可動域“は常に向き合うテーマである。
“関節可動域“のトラブルは、疾患・外傷によって引き起こされ、様々な機能不全をもたらす。
そのため、理学療法士は“関節可動域を取り扱う専門家“と捉えることができる。
しかし、常に対峙するテーマでありながら、学校で学ぶ“それ“は検査・測定に重点が置かれていることが多い。
また、病態や基本的動作解析との関連性を解説した書籍は少ない為、“臨床現場に活かせる“関節可動域の知識を習得できているとは言い難い。
そこで本書では「各関節の制限因子」「基礎知識」「運動器疾患」「中枢神経疾患」という4つのテーマに分けて、各分野のエキスパートが“臨床現場に活かせる“関節可動域について徹底的に掘り下げている。
その数、圧巻の30項目。
本書を通じて奥深き可動域の全貌に触れることで、あなたの可能性を大きく広げることができるだろう。
テーマ①
各関節の制限因子
- 肩関節の可動域制限と制限因子:千葉慎一
- 股関節の可動域制限と制限因子:永井聡
- 膝関節の可動域制限と制限因子:今屋健
- 足関節・足部の可動域制限と制限因子:園部俊晴
- 脊柱の可動域制限と制限因子:弓岡光徳/廣瀬浩昭/弓岡まみ
テーマ②
関節可動域の基礎知識
- 基本的動作に必要な関節可動域と制限を呈することの影響:木林勉/河野光伸/酒野直樹/川口朋子/木林遥香
- 関節の構造と可動性:佐藤香緒里/堀紀代美
- 若年者と高齢者の関節構造と可動域の相違:中村壮大
- 動物実験による関節の病態:沖田実
- 関節疾患に及ぼす関節可動域の理学療法評価の基本概要:佐々木賢太郎
テーマ③
運動器疾患
- 五十肩の関節可動域の病態と理学療法:中山昇平
- 変形性膝関節症の関節可動域の病態と理学療法:園部俊晴
- 変形性股関節症の関節可動域の病態と理学療法:丹羽雄大
- 脊柱管狭窄症の関節可動域の病態と理学療法:藤森大吾/成田崇矢
- 骨折による関節可動域の病態と理学療法:神戸晃男
- 野球肩・肘の関節可動域の病態と理学療法:板野哲也/亀田淳/立花孝
- 膝関節の靭帯損傷の関節可動域の病態と理学療法:古川裕之
- 熱傷の関節可動域の病態と理学療法:對東俊介
- 側弯症の関節可動域の病態と理学療法:峰久京子
- 骨粗鬆症に伴う関節可動域制限とその理学療法:峯松亮
- 関節可動域拡大および制限として応用するテーピング:福井勉
- 拘縮予防・改善のための装具療法:小嶋功
- 関節可動域改善のための物理療法の臨床応用:前重伯壮
テーマ④
中枢神経疾患
- パーキンソン病の関節可動域の病態と理学療法:奥山紘平/松尾善美
- 脳性麻痺の関節可動域の病態と理学療法:冨田秀仁/川口大輔
- 脳血管損傷の関節可動域の病態と理学療法:土山裕之
追加テーマ
関節可動域に関するコラム
- 理学療法における各種介入の併用の重要性:奈良勲
- 拘縮と痛みとの関係性:赤羽根良和
- 生活期リハビリテーションにおける関節可動域へのアプローチ:吉井智晴
- 関節可動域を征する者は運動機能をも征する:園部俊晴
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=173375342
肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版

本書は、10年前に出版された『肩関節拘縮の評価と運動療法』の改訂版です。
シリーズ5万部を越えている『拘縮』シリーズでも特に人気の本書に新たに実技映像を追加し、読者がより効果的に学ぶことができるようになっています。改訂版では、イラストや図が一新され、より解説がイメージしやすくなっています。
また、肩関節拘縮の評価方法から、運動療法の実施方法までを詳しく解説し、運動療法に興味がある理学療法士やスポーツトレーナー、医師、学生などに向けた内容となっています。
QRコードを読み取ることで、本書で紹介された運動療法を実際に実践している著者の解説映像を59本視聴することができます。本書を読むことで、肩関節拘縮の適切な評価と効果的な運動療法の実際を学ぶことができます。前作を読んだ読者はもちろん、新たに知見をブラッシュアップしたい方にもオススメの書籍となっています。
Point 01
現場に役立つことに徹底的にこだわった内容
肩関節機能障害はその機能解剖学的に複雑な構造や病態把握の難しさから苦手とするセラピストが多い疾患です。本書は機能解剖学の視点から、1つ1つの組織機能や病態について分かりやすく紐解いていきます。そして、それぞれの組織や病態ごとの具体的な評価やアプローチの方法を臨床現場の目線で解説していきます。
Point 02
著者、赤羽根良和による実技映像を59本収録
今回のリニューアルの大きなポイントとして、著者の赤羽根良和の実技解説動画を収録しています。各アプローチの文章中にあるQRコードを読み取ることで、文章に対応した実技動画を視聴することができます。本書の内容と映像を一緒に観ることで、より実際の臨床に活かすことができるようになりました。
Point 03
イラストと写真を刷新。さらに分かりやすく
分かりやすい内容はそのままに、イラストと写真を刷新しました。著者とデザイナーがディスカッションを繰り返しながら更にブラッシュアップしたので、複雑な肩関節の構造体をより理解しやすくなっています。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=174677725
成田崇矢の臨床 腰痛

運動器疾患の治療で避けては通れないのが腰痛改善。しかし、その治療結果に相手が、そして自分自身が納得していない臨床家は多いはず。様々な治療法を学んだり、文献を読み漁ってもなぜ、結果につながらなかったのかが本書を読めば納得できるはずだ。
本書では腰痛治療の極意を次のように示した。それは、『痛みを発生させている組織を仮説し、その組織および、その組織への負荷を改善させる』だ。言葉にするとシンプルだが、実際には多くの治療家が『原因組織の仮説』の段階でつまづいている。なぜなら、一般的に腰痛の85%は「非特異的腰痛」と呼ばれ、原因が特定しきれないと言われ、かつその言葉に逃げてきたからだ。
しかし、筆者の成田崇矢はこれらを「機能的腰痛」と名付け、大半の腰痛は機能を変えれば痛みも変わると断言している。さらに、この『機能的腰痛』は「椎間関節障害」「仙腸関節障害」「椎間板障害」「筋・筋膜障害」の4つの病態に収まるとしている。それぞれの鑑別・評価・治療法を体得することで、その場で改善することが可能になった。本書を通じて適切な仮説と、適切な検証の方法を学べば、腰痛患者に対し、「何をすべきか」がみえてくるはずだ。
さあ、今こそ圧倒的な結果を出すための“確信”と“自信”を手に入れよう。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=173375342
臨床実習生・若手PTのための理学療法実践ナビ 脳血管疾患

運動器疾患編に続き、第2弾がついに発売
理学療法士になるために避けては通れない臨床実習。理学療法の現場を間近で体験し、臨床スキルはもちろん、医療者としての態度や姿勢を学ぶことができる機会でもあります。
しかし、多くの学生が臨床実習に対し、「つらい」「たいへん」など、ネガティブな思いを抱いているようです。このような背景から、「理学療法って楽しい」 と感じて臨床実習を終える事は少ないようです。また多くの実習指導者も、学生に対し「学生に対する指導方法なんて教わってないからよく分からない」などの思いを抱いているようです。
こうした実情を変え、「理学療法って、こんな魅力的な仕事なんだ」と、将来に 向けてワクワクするような思いで、就職できるような状況に変えたいと切に思っています。こうした思いからつくられたのが、この書籍です。
臨床実習で学ぶ脳血管疾患は、ある程度限定されています。そのため、理学療法士を目指す学生が臨床実習でよく診る疾患を限定し、効果的に学ぶためのバイブルとなる書籍にすることを目標に、各筆者とディスカッションを重ねながら本書を作成しました。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=172265777
臨床に役立つ歩行運動学

身に付けろ、自分史上、最高の分析力!
リハビリテーションのニーズとして頻出する〝歩行の再獲得〟
こうしたニーズに応えるために、私たちセラピストは最も歩行に精通していなければならない職種であるといえる。
しかし、歩行はその動作の複雑性から『歩行分析が苦手』、または『現象を捉えることができたとしても臨床に活かす事ができない』と悩んでいるセラピストも多い。
そこで今回、歩行の再獲得につながるバイブルとなる書籍が完成した。
臨床歩行分析研究会の会長を歴任し、歩行の研究者として、そして臨床家として活躍する理学療法士、畠中泰彦先生が執筆している。
理論科学だけでなく、臨床家としての経験科学に基づくトピックも豊富にあるため、学んだ知識を実際の臨床に活かすことができる内容となっている。第4章では正常歩行からの逸脱パターンを71種類も紹介している。そして、それぞれのパターンの直接的要因と間接的原因を徹底解説しているため、歩行分析からの臨床推論に大いに役立つように作られている。
本書はプロの臨床家向けとして構成された本でもあるため、教科書的に1ページから読み進めるのも良し、そして臨床場面で感じた疑問を解き明かす際に対象のページを読み込むのも良しの理想的な作りになっている。何度も「実践」と「読み返し」を繰り返すことによって、最高の分析能力を手に入れることができるだろう。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=171136429
スポーツ外傷・障害に対する術後のリハビリテーション 改訂第3版

これがスポーツリハだ!
プロスポーツ選手が集まる日本屈指の病院のリハビリのノウハウを大公開!10年以上読まれ続けているスポーツリハの決定版が装い新たにリニューアル!
全国のプロスポーツ選手が集まる病院、関東労災病院。日本屈指の病院で行われているリハビリのノウハウが、この本に余すことなく詰め込まれている。本書は2010年に初版が発売されて以来、1度目の改訂を挟みながら、多くのセラピストに読まれ続けているバイブルである。9年ぶり2度目のリニューアルとなる今回は、多くの手術症例に基づいた最新の臨床成績データをふんだんに盛り込み、そこから得られたリハビリの新たな知見が追加されている。写真や図も更に分かりやすくなり、ページ総数は500ページを超えるボリュームとなっている。本書は理学療法士・柔道整復師・トレーナーなどスポーツリハに関わる全てのセラピストの為の手引き書である。最新のスポーツリハの理論と技術を学んでほしい。
ご購入はこちら
→https://www.amazon.co.jp/dp/4904862546
足関節拘縮の評価と運動療法

あの林典雄先生監修の関節拘縮シリーズ最新作がついに登場します。土台にして軸となる足関節拘縮について、臨床の第一線で活躍する気鋭の理学療法士、村野勇先生が徹底解説。超音波画像で可視化された拘縮病態を深堀りしたことで、新時代の理学療法評価と運動療法を学ぶことができます。
徹底的な医学論文からの紐付けによる信頼性、そして臨床に即した超音波画像による組織の動態観察から、50年前のセラピストが読んでも、そして50年後のセラピストが読んでも大変勉強になる内容になっています。
今回は超音波画像に基づいた軟部組織の動態を動画でみることができます。しかも症例を交えているため、正常な動きと異常な動きの比較が可能です。このため、超音波がなくても組織が動くイメージを持つことができるため、臨床でどのように徒手操作を行えばよいかが分かります。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=169831040
臨床実習生・若手PTのための理学療法実践ナビ 運動器疾患編

充実した臨床実習を送るためには
理学療法士になるために避けては通れない臨床実習。理学療法の現場を間近で体験し、臨床スキルはもちろん、医療者としての態度や姿勢を学ぶことができる機会でもあります。
しかし、多くの学生が臨床実習に対し、「つらい」「たいへん」など、ネガティブな思いを抱いているようです。このような背景から、「理学療法って楽しい」 と感じて臨床実習を終える事は少ないようです。また多くの実習指導者も、学生に対し「学生に対する指導方法なんて教わってないからよく分からない」などの思いを抱いているようです。
こうした実情を変え、「理学療法って、こんな魅力的な仕事なんだ」と、将来に 向けてワクワクするような思いで、就職できるような状況に変えたいと切に思っています。こうした思いからつくられたのが、この書籍です。
臨床実習で学ぶ運動器疾患は、ある程度限定されています。そのため、理学療法士を目指す学生が臨床実習でよく診る疾患を限定し、効果的に学ぶためのバイブルとなる書籍にすることを目標に、各筆者とディスカッションを重ねながら本書を作成しました。
この書籍に書かれた内容を通じ、臨床実習を効果的に学び、1つの実習施設から多くのこと学び取れるように作られています。 そして、資格を取得することが目的に終わらず、就職してからも成長していける礎になれば、これほど嬉しいことはありません。
責任編集 園部 俊晴
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=168125691
基礎科学を融合した理学療法推論の実際

一流臨床家に共通しているのはレベルの高い臨床推論を展開していることです。
どんなに豊富な知識を持っていても、
どんなに素晴らしい手技を持っていても、
その評価とアプローチをつなげる『臨床推論』抜きでは臨床で結果を出すことはできません。
現在、最新の知見やアプローチを学ぶコンテンツは豊富にありますが、臨床推論を学ぶことができるコンテンツは殆どありません。
そこで今回、元・理学療法協会 会長の奈良勲先生が選抜した、
様々なジャンルの理学療法に携わるエキスパートに依頼して、各分野の第一線ではどのような臨床推論を展開しているのかを1冊の本にまとめました。
広範な分野の理学療法推論を掲載しているので、理学療法の可能性の広さを感じることができます。
また、自分の知らない世界を知ることによって、臨床推論の幅を広げることに役立つはずです。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=167402577
変形性膝関節症の保存療法

変形性膝関節における理学療法の良質なエビデンスは多数報告されていますが、臨床現場では保存的治療戦略の確立には至っているとは言えません。
また、現在15万人以上の理学療法士がいる中で、変形性膝関節症の保存療法をしっかり理解して、患者を治療している人はとても少ないと言えます。
実際に、変形性膝関節症の保存療法として、あまり自信がなく、「何をしたら良いかわからない」と、そう感じているセラピストは、少なくないのではないでしょうか。
その原因の1つとして、変形性膝関節症によって起こる機能障害の仮説検証を繰り返していく過程が十分に行えていないことが挙げられます。
仮説検証とは対象者の訴えや症状から病態を推測し、仮説に基づき適切な検査法を選択し、対象者の最も適した介入方法を決定していく一連の過程のことを言います。この仮説検証を日々の臨床で繰り返していくことが良質な医療を患者に提供するために不可欠です。
『変形性膝関節症の保存療法』では、この仮説検証をする上で必要な知識やノウハウを余すことなく詰め込こんでいます。山田英司先生が遺した本書が、変形性膝関節症の保存療法における、新しいスタンダードとなることを確信しています。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=165985473
脳卒中運動学

脳血管疾患を発症すると上位運動ニューロンが障害されるため、 運動麻痺や感覚障害を生じることがあります。
また、運動と現象という視点で見ると、病的共同運動パターンや連合反応、ぶん回し歩行など、健常者では見られない病的な運動と現象が生じるようになります。多くの脳卒中リハビリテーション分野の書籍では、これらの現象を脳科学から解説されるため、苦手意識を持つ方は少なくないはずです。また、脳科学で異常や運動現象を理解したとしても、そこから効果的な評価と運動療法に繋げることができない方が多いと思います。
そこで今回、脳機能だけの解釈ではなく、我々理学療法士が持っている解剖学や運動学の知識で多くの片麻痺患者の症状を説明した革新的な書籍が完成しました。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=163086995
この書籍の解説動画は下記から
→https://www.youtube.com/watch?v=JTwzwQFmS-M&t=13s
体幹と骨盤の評価と運動療法 改訂版

[概要]
身体のどの部位の治療に当たるにしても、体幹の機能が大きく関与することは臨床を通して、漠然と感じていたことだと思います。その漠然と感じていたものが、本書の分かりやすいイラストや写真によって、イメージすることが可能になっています。さらに、膨大な論文や研究データを基に、臨床で求められる体幹機能の改善方法について分かりやすく解説したことで、1年目のセラピストでも体幹の機能が深く理解できるようになっています。
[改訂版について]
今回のリニューアル改定では、特に4章「座位における体幹・骨盤の機能と運動療法」と、5章「立位における体幹・骨盤の機能と運動療法」に力をいれております。各動作の項目(4章では4動作、5章では3動作)ごとに対する運動療法のポイントを、臨床に即した形で解説しています。各動作に必要な筋活動と動作の捉え方が理解出来るようになれば、体幹の機能を高めながら身体の各部位の治療を展開することも可能です。臨床の幅が広がり、目的をもった運動療法を展開するためにも、本書を読み進めて頂ければ幸いです。
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=163085880
膝関節 痛みを改善する為の方程式

私が臨床家として飛躍的に成長したと感じられるようになったのは、40歳になってからでした。
成長にはいくつかのきっかけがありましたが、中でも大きなきっかけが3つありました。
これについて、この書籍内で深掘りして説明しています。
あなたは目の前のその膝の、「痛みを発している組織をいえますか?」「痛みの力学的な原因
をいえますか?」「痛みをその場で取ることができますか?」 自信がない という人は......
...、すぐにこの本を読み進めてください。毎日の臨床が最高に楽しくなると思います。
ご購入はこちら
→https://amzn.to/39gvITv
この書籍の解説動画は下記から
→https://www.youtube.com/watch?v=wFtBFltLQyE
マッスルインバランス 改善の為の機能的運動療法ガイドブック

ベストセラーの著者「荒木茂先生」の新刊「マッスルインバランス改善の為の機能的運動療法ガイドブック」がついに発売しました。掲載エクササイズ213種類!姿勢や動作評価から運動療法を医学的視点で展開し、各々の運動の代償動作まで掲載しているこれまでにない運動療法の書籍と言えます。「運動療法の引き出しがもっとほしい」と感じている方や「運動療法で症例を変えたい」と思っている方には必見です(^-^)
ご購入はこちら
→https://motion-medical.co.jp/?pid=155528065
この書籍の解説動画は下記から
→https://www.youtube.com/watch?v=CA1IAuf09ic
入谷誠の理学療法

私は理学療法士のトップランナーをたくさん見てきましたが、その中でも入谷誠先生は、類をみない傑物であったと感じています。20年以上もの間、入谷誠の弟子として臨床の変遷を見てきた立場で言うと、入谷先生は強い哲学を持ち、常に成長を求め続けた臨床家でした。日本中から症状に悩む患者が訪れ、その臨床にはいつも感動に溢れていました。
入谷先生の臨床の神髄は力学にあったと感じます。この書籍には、入谷先生が30年以上に渡り築いてきた力学的推論の治療概念が詰まっています。難解と感じることも多いと思いますが、ただの技術書ではなく、伝説の臨床家の想いの1冊であることをご理解いただき、読み進めることで気づくことがたくさんあると思います。入谷先生の集大成となったこの1冊が皆様の臨床の成長にお役に立てれば、これほど嬉しいことはありません。
ご購入はこちら
→ https://amzn.to/3bjqs04
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=sH2gHO96xqI
膝関節拘縮の評価と運動療法

林典雄先生監修の大ヒットシリーズの「膝関節」が出版されました。組織学的仮説検証行うにあたり基盤となる書籍だと思います。筆者の橋本貴幸先生が、どのように評価し、どのように治療しているのかが明確に書かれています。全編集に園部がかかわりました(^^♪
運動と医学の出版社の最高の自信作の一つです。
ご購入はこちら
→ https://motion-medical.co.jp/?pid=147474105
この書籍の解説動画は下記から
→ https://youtube.com/video/gsz_sl8zcMY/
股関節拘縮の評価と運動療法

林典雄先生監修の大ヒットシリーズの「股関節」が出版されました。組織学的仮説検証行うにあたり基盤となる書籍だと思います。筆者の熊谷匡晃先生が、どのように評価し、どのように治療しているのかが明確に書かれています。また歩行についても詳しく書かれているので、運動学の勉強にもなりますよ。
運動と医学の出版社の最高の自信作の一つです。
ご購入はこちら
→ https://motion-medical.co.jp/?pid=146932896
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=A_805TScfQA
腰痛の原因と治療

整形外科医の髙橋弦先生と、園部の共著の書籍『腰痛の原因と治療』が出版されました。この書籍で記載されている運動器疼痛症候論という概念は、髙橋弦先生独自のアイデアであり、類書は世界的にも存在しないと思います。基礎医学(神経科学・疼痛学)、整形外科学、ペインクリニック、理学療法学(特に運動療法)、精神医学の考え方の解離を統合する架け橋になる概念ではないかと考えています。
リハビリは園部が書いてますよ(^_^)
ご購入はこちら
→ https://motion-medical.co.jp/?pid=146932717
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=ix6J3aroL7g
五十肩の評価と運動療法

この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=A0WoeravDuo
ご購入はこちら
→ https://motion-medical.co.jp/?pid=145162910
肩関節拘縮の評価と運動療法(臨床編)

林典雄先生監修! 赤羽根良和先生執筆の大ヒット書籍!
赤羽根先生が実際に担当した10症例を鋭く解説しています。素晴らしい臨床家が、どのように評価し、どのように治療しているのかが明確に書かれています。
運動と医学の出版社の最高の自信作の一つです。
この書籍の解説動画は下記から
→ https://youtu.be/h2RjIu2YhLQ
林典雄先生の運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 下肢編


林典雄先生は、「組織学的推論」の王様です。機能解剖の知識と、病態を解釈する力においては、林典雄先生は最高の力を有しています。
本書を読み終わった後に、
「運動器疾患っておもしろい!」
「運動器疾患をさらに深く学びたい!」
と感じるはずです。
この書籍の園部の解説を下記のURLでご覧下さい。
→ https://youtu.be/qlNQ_o287Ck
→ 下肢編 ご購入はコチラ
→ 上肢編 ご購入はコチラ
機能解剖学的にみた膝関節疾患に対する理学療法

臨床に即した、臨床に役立つ最高の書籍です!
この書籍の校正に携わり、機能解剖をここまで駆使する赤羽根良和をさすが!と、改めて痛感しました。この書籍の100の臨床のヒントをすべて網羅することで、確かな臨床の変化が得られると確信しています。
この書籍の園部の解説を下記のURLでご覧下さい。
→ https://www.youtube.com/watch?v=BaehKiDv8f4
→ ご購入はコチラ
マッスルインバランスの理学療法
世界を見てきた理学療法士・荒木茂の集大成がここにある!
理学療法の展開を変えることを理解頂けると思います。
その意味は下記の映像見ればわかると思います。
→ https://www.youtube.com/watch?v=v6g_J_wml6E
寝たきりをつくらない介護予防運動~~理論と実際~~
高齢化率の上昇は、これから30年以上も止まることがありません。2055年には、なんと高齢化率が39.9%に達すると推計されています。このことを知ると、今後、我々療法士に、国が、そして社会が、最も要求するものは何だと思いますか。
それは・・・
「寝たきり」を減らし、そして「家族の介護」を少なくすることが、絶対的な要求として、社会がさらに望むようになります。
そしてそれができる療法士は絶対に社会から要求される人材になります。もし自分の将来に不安を感じている療法士がいましたら、この本をぜひ読んで欲しいんです。
その意味は下記の映像見ればわかると思います。
→ https://youtu.be/tVVauAYnTIc
ご購入はコチラ
→ http://motion-medical.co.jp/?pid=126486320
腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック
この書籍についているDVDをみれば、絶対、「すげえ!」と思うはずです。
この書籍の園部の解説を下記のURLでご覧下さい。
→ https://youtu.be/vxWivfp_hWs
腰痛を組織学的仮説検証の切り口から考える上で、素晴らしい書籍です!
→ ご購入はコチラ
リハビリの先生が教える「健康寿命が10年延びるからだのつくり方」
この書籍は、一般書でありながら、私の臨床の全てが詰まった最高の書籍ができたと思っています! 我々リハビリの先生は歳をとってくると、“どこが硬くなるのか・・・”、“どこが変形してくるのか・・・”、“どこが弱くなるのか・・・”といったことを最もよく知っていると思います。つまり、健康寿命に最も貢献できる職種の一つです。この本を読んでいただければ、我々療法士が今後の高齢化社会に何を成すべきかが分かっていただけると思います。
そして、疾病によって生じた障害を治療することはもちろん大切ですですが・・・、健康寿命に貢献することで、社会も、利用者も、その家族も、そして我々療法士にとっても、みんなが幸せになる社会貢献ができることを分かっていただけると思います。
共感しましたら、SNSなどで広く広めて頂き、「リハビリの先生が教える・・・」のキャッチから始まるこの本をみんなの力でヒット作にのし上げて頂けると大変嬉しく思います。
療法士の臨床にも必ず役立つ内容であることを約束します!!
→ご購入はコチラ
リハビリの先生が教える「健康寿命が10年延びるからだのつくり方」
脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ ~基礎編~
日本人国際インストラクターが執筆した貴重な書籍!ボバースアプローチは、世界で最も普及した脳卒中のリハビリテーション治療概念です。私自身の成長に大きく貢献した書籍です!
→ ご購入はコチラ
脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ臨床編
この書籍にはなんと筆者の古沢先生が実際に患者を治療した臨床映像が付いています。日本最高峰の療法士の実際の治療を見れる機会は滅多にないと思います。
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=r_VzXPQzmKY
→ ご購入はコチラ
アキレス腱断裂の治療
この本の筆者の内山英司先生は、タイトルにあるように、「名医」と呼ばわりにふさわしい偉大な医師であることを、一緒に働いてきた立場として断言できます。
そして、このような真に臨床に即した素晴らしい書籍に関わらせていただいたことをとても光栄に感じております。
この書籍の重要性について、私なりに下記の映像にまとめましたので、是非ご覧ください。
→ https://www.youtube.com/watch?v=at3WZS90YO0
→ ご購入はコチラ
皮膚テーピング~皮膚運動学の臨床応用
皮膚運動学の最もバイブルとなる書籍です!海外でも発売。「皮膚は運動療法の一画を担うほどの重要な器管である」ということが理解できます。
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=j4CQLYzL6YQ
→ ご購入はコチラ
肩関節拘縮の評価と運動療法
大ヒット書籍!組織学的仮説検証行うにあたり基盤となる書籍だと思います。また筆者の赤羽根先生は私の友人であり、本物の臨床家です。
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=6qp9dwfXXwE
→ ご購入はコチラ
入谷式足底板 ~基礎編~(DVD付き)
私の師の入谷誠先生が初めて出版した単著。入谷先生は私が出会った最も優れた臨床家であり、世界最高峰の臨床家です。入谷先生の考えを広めることは、私の人生の使命の1つです。
この書籍の解説動画は下記から
https://www.youtube.com/watch?v=fULv2wsmn64
→ ご購入はコチラ
改訂版「スポーツ外傷・障害に対する術後のリハビリテーション」
スポーツ分野において、手術件数日本一を誇る関東労災病院のスタッフにより執筆。多数の養成校で教科書として採用され、スポーツ以外の分野でも役立つことを約束できる書籍です。
この書籍の解説動画は下記から
https://www.youtube.com/watch?v=3ZrEGidJs3A
→ ご購入はコチラ
改訂版・「効果的な文章の書き方」入門
伝えたいことをわかりやすく、短時間で、書く技術を記載。また自分の考えていることがまとまりやすくなり、専門職として成長するためのツールとなります。
この書籍の解説動画は下記から
→ https://www.youtube.com/watch?v=gB-SZ8Jch_k
→ ご購入はコチラ
おすすめ記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
















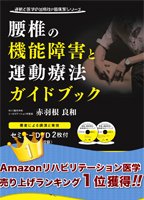
















この記事へのコメントはありません。